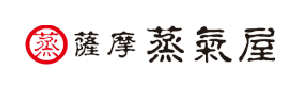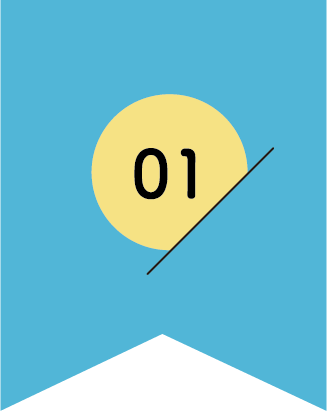
二人の生みの親と開催のきっかけ
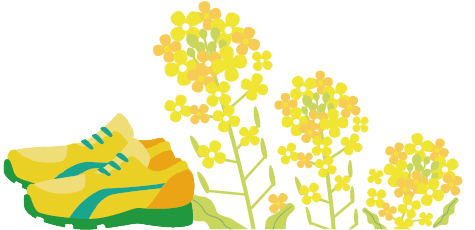
1981(昭和56)年、東京の大手旅行会社社員、茂木氏と金田氏が指宿を訪れました。彼らは、ジョギング仲間を誘っては、ホノルルやボストンなどの海外の市民マラソン大会へ繰り出すほどの大のマラソン愛好家。茂木氏と金田氏は指宿で温泉を楽しみ、充実した宿泊施設を目の当たりにします。そして、九州最大の湖 池田湖や日本百名山にも選ばれている開聞岳、眺望絶佳な長崎鼻、竹山など、美しい自然がまるで宝石を散りばめたかのように点在しているのを見て、ランナーの勘で、これらを一周すれば42kmほどになると感じました。新年にここを走りたい。冬でも暖かい指宿なら大丈夫。2人は「マラソン大会を企画してほしい。ランナーは東京から仲間を連れてきます。」と指宿市観光協会に依頼したのです。
当時の指宿は、観光客が激減し、正月が過ぎるとどのホテルもがら空きの状態でした。昭和40年代の指宿は新婚旅行のメッカでしたが、昭和50年代に入ると行き先はグアムやハワイなどの海外が一般的に。加えてオイルショックが追い討ちをかけ、旅行需要は大幅減。大手のホテルが次々と姿を消していました。観光協会の役員は、この提案を了承したのです。
こうして1982(昭和57)年1月16日、第1回大会が、「指宿温泉マラソン大会」の名で実現したのです。

第1回スタート地点(池田湖畔)

第1回折り返し地点

第2回折り返し地点

10kmの部に出場した宗兄弟
(第2回招待選手)
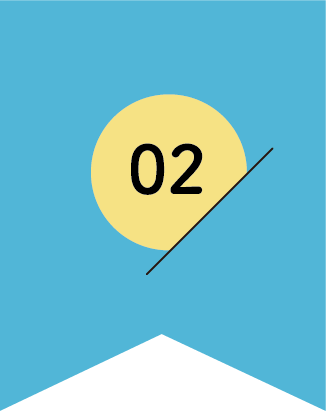
育ての親 山田敬蔵選手と「金栗杯」
この小さな大会に華を添えてくださったのが、山田敬蔵選手でした。山田選手は、大河ドラマ「いだてん」の主人公にもなった“日本マラソンの父”金栗四三氏の愛弟子です。1953(昭和28)年のボストンマラソンを世界新記録で優勝し、戦後復興の途上にあった日本に夢と希望を与えた伝説の選手です。その活躍は「心臓破りの坂」として映画にもなりました。
旅行会社に入社した山田選手は、マラソンを観光資源と捉え、地方にマラソン大会を広めようと観光地を巡っていました。指宿に来訪したのは、茂木氏と金田氏の来訪とほぼ同時期。大会立ち上げに向け一緒に動きました。いぶすき菜の花マラソンの優勝カップは「金栗杯」ですが、これは、金栗四三氏の“地方のマラソンスポーツを普及発展させたい”という願いから名前をいただき、本マラソン大会が始まる年に山田選手から贈られたものなのです。
山田敬蔵選手は、第1回から第31回(2012(平成24)年)まで、ほぼ全ての大会に招待選手としてご参加いただき、大会のコンセプトや運営について毎回適切なアドバイスをくださいました。茂木氏と金田氏が「生みの親」ならば、山田選手はまさしく「育ての親」と言えるでしょう。

山田敬蔵氏(右)
金栗四三氏(左)

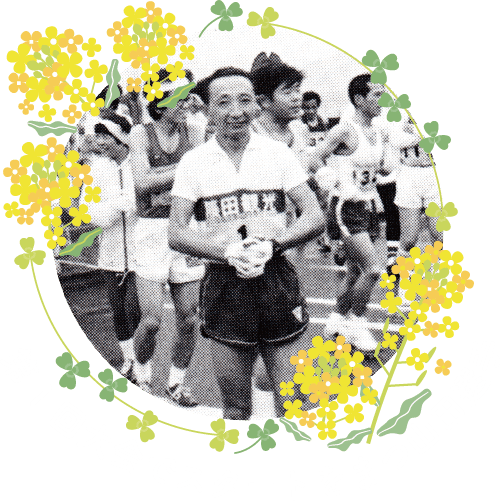
山田敬蔵(1927-2020)
秋田県大館市生まれ。9歳の時にオリンピック出場を決意。我流で走り始めるが、日本マラソンの父・金栗四三に見いだされ順調に記録を伸ばした。戦後、1952(昭和27)年のヘルシンキ五輪に出場。翌年のボストンマラソンでは世界記録で優勝。第一線を退いた後も走る喜びを伝えるために走り続け、生涯に地球9周分、36万キロを走りぬいた。

金栗四三(1891-1983)
熊本県和水町に生まれ、半生を同県玉名市で過ごす。1912(明治45)年、日本人として初めてオリンピックに出場。シューズの改良や箱根駅伝の発案など、生涯にわたり日本マラソン界の発展、スポーツの振興に尽力した。
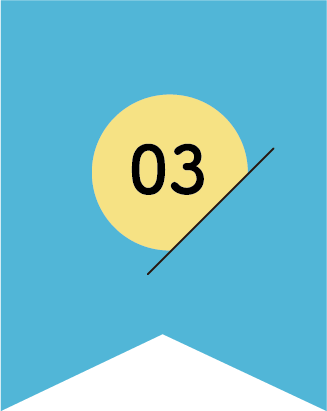
「菜の花マラソン」のはじまりと大会の発展
無事に第1回大会を開催できたものの、天気は最悪、苦労ばかりだったため、「来年はやめよう」という声も上がりました。しかし、東京から走りに来てくれたランナーの喜びの顔が大会役員の心に焼きついていたことが、第2回の開催を後押ししました。
第2回の参加者は423人。第3回は841人、第4回が1,474人と、参加者は徐々に増えていきました。
テーマを“菜の花”へ〜観賞用への品種改良〜
第2回までは「指宿温泉マラソン大会」の名称で実施していましたが、別府温泉マラソンと重なるなどの問題がありました。そこで第3回へ向けて、当時の指宿市・山川町・開聞町の1市2町で実行委員会の組織を作り新たなテーマを模索、菜種油用の菜の花の活用が決まりました。大会名も「指宿菜の花マラソン大会」に改め、休耕地を利用した本格的な菜の花の植栽が始まりました。
しかし、菜種油用の菜の花は背が小さく、花も1週間程度しか持たないなどの課題がありました。そこで鹿児島大学に依頼し、大根花とのかけ合わせや、インドから取り寄せた青い大根花などとのかけ合わせを行いました。品種改良はなかなかうまくいきませんでしたが、5年の歳月をかけた試行錯誤の末、観賞用の菜の花が完成。今では1,000万本の菜の花がランナーを出迎えます。
ちなみに、菜の花の花言葉の一つは「元気いっぱい」。ランナーの応援にぴったりの花なのです。
1986(昭和61)年には、九州各地でのキャンペーンを開始しました。ジョギングランナーが練習する場所を直接訪ね、一人ひとりに葉の花の種と参加申込書を配って歩きました。この地道な活動の甲斐あって、参加者はその数を急激に伸ばし、昭和62年の第6回で5,000人を突破。平成4年の第11回で待望の1万人を越えたのです。

第4回からはKKB鹿児島放送との共催。開局記念の地域のイベントとして菜の花マラソンを選んでいただいた。

池田湖に咲き誇る菜の花(第6回)

コースや表彰式会場など、至る所に葉の花が置かれた(第6回)



第6回からは沿道にフラッグを設置。

指宿駅前の看板とフラッグ

第6回・第7回は知林ヶ島と錦江湾を眺む海沿いの道もコースとなっていた


第6回大会の様子

81歳の仮装ランナー(第6回)


第二十回の記念大会(平成十三年)南国指宿では珍しい粉雪の舞う天候



第39回大会の様子(写真は川内優輝選手。第38回大会では、大会新記録で優勝)
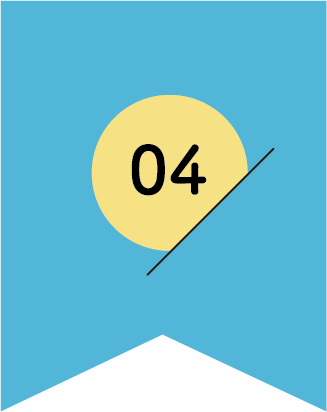
「おもてなし日本一」のマラソン大会を目指して
参加者が大幅に増えていった一番の理由は、「おもてなし日本一のマラソン大会」を目指そうという大きな目標を掲げたことにあるでしょう。大会の目的を、「地域ぐるみの観光浮揚とまちおこし」と設定し、実行委員会のメンバー1人ひとりがこれを肝に銘じて動き出したのです。
疲れた身体をマッサージしてあげよう、特産品のさつまいもや鰹節を使った茶節を振る舞おう、温かいそばやうどん、正月らしいぜんざいを提供しよう、自慢の温泉を無料開放しよう•••。大会を運営する人々の思いが住民へも伝わり、それぞれの地域や立場で、コースのあちこちでそれぞれの「おもてなし」をしてくださるようになりました。また、事前の菜の花の植え込みや旗立て、当日の大会運営にあたっては、2,000人を超えるボランティアの方々が積極的に協力してくれています。
こうした「人の和」あってこそ、「いぶすき菜の花マラソン」は、全国を代表する市民マラソン大会へと成長したのです。

平成10年 さつまいもの炊き出し

平成15年 マッサージボランティア





「菜の花のまち」の歴史
〜幕末の菜種改革〜
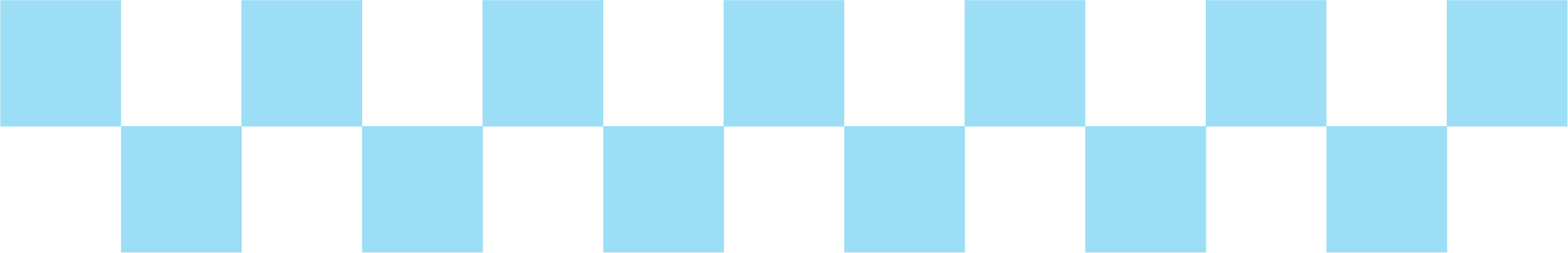
菜の花は、指宿市の「市の花」でもあります。菜の花と指宿との関係は古く、その始まりは江戸時代までさかのぼります。薩摩藩では元々、菜の花が食用・菜種油用に栽培され、大阪に出荷していました。しかし、一俵あたりの容量が少なく土砂も混じる始末で、粗悪品として安値で取引されていたのです。
そこで、菜種生産を改良し特産品化を図ったのが、天保年間(1830~1844)に10代藩主島津斉興の命で藩の財政改革を担った家老 調所広郷と、山川郷の地頭職 海老原清煕でした。調所と海老原は、まず他藩から牛馬や鯨、鰹の骨粉飼料を取り寄せて藩内に配給し、土づくりを行うことで菜種を増産しました。そして選別機(唐箕)を導入し、収穫の際に混じった砂を風力で選別し品質を向上させました。さらに、紙袋に入れた菜種を俵に入れて出荷することで、一俵あたりの容量を約12%増量しました。これらの対策によって、鹿児島藩産の菜種は品質も良く実入も充分となり、値段は改革前の約2倍に。他藩産の菜種に比べ最高価格となりました。海老原は「山川は良水と海運の便を兼ねる一等地であり、菜種油絞り用の水車を置き、各地から菜種を集め製油すべき」と記していますが、江戸の講釈師 伊藤凌舎の旅日記に「山川湊、水車にて油しめをしているのは見物である」との記述があることから、実際に水車が置かれていたことがわかります。
また、天璋院篤姫の父である島津忠剛も、海老原清煕に相談し指宿における菜種生産を奨励したといいます。こうして指宿は、菜種の全国一大産地となったのです。
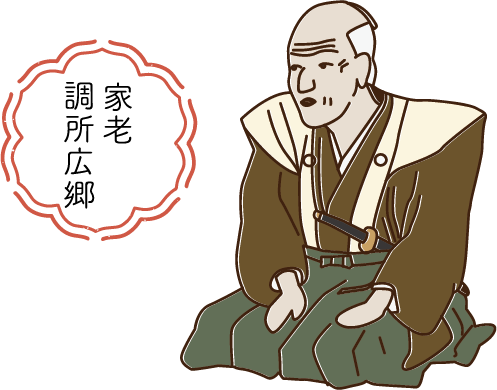
【参考文献】芳 即正1987『調所広郷』吉川弘文館
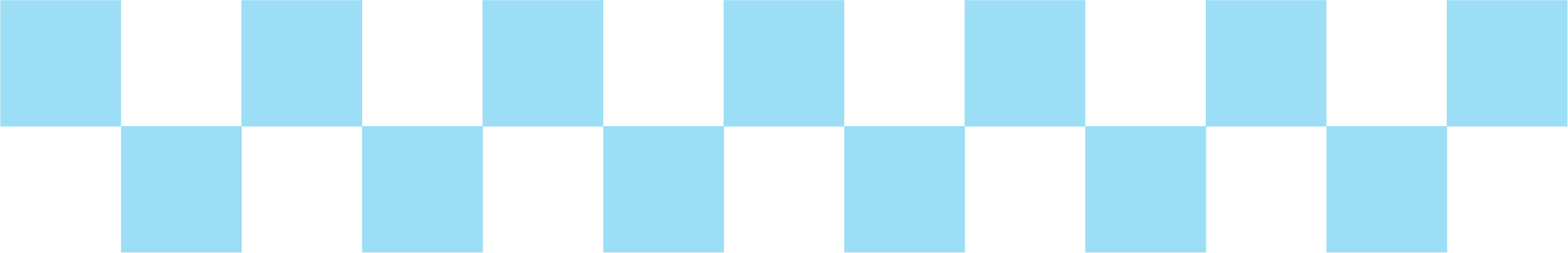
第40回Tシャツロゴ

歴代Tシャツロゴ






 大会の特色
大会の特色